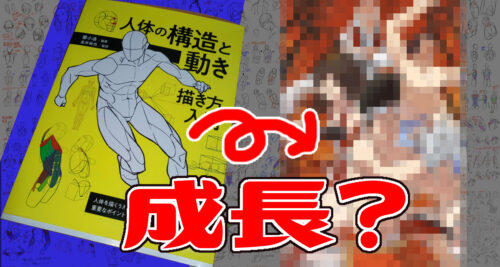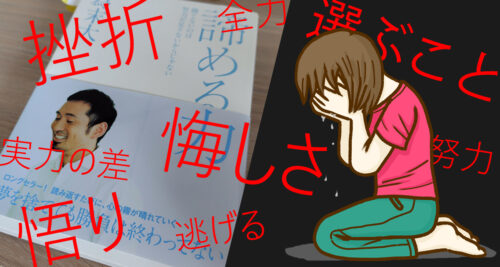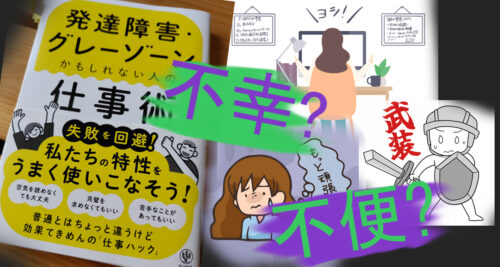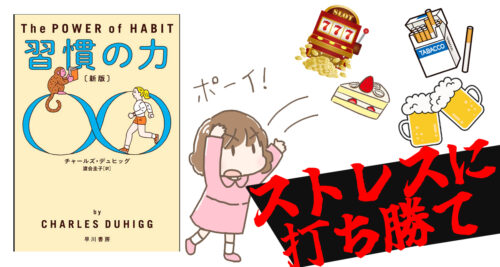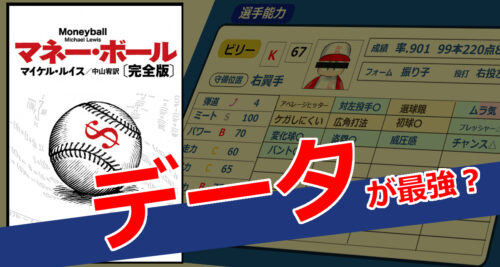ちょっと前に、誰かの記事で「戦略的交渉入門」という書籍が紹介されていました。
今まで疑問だった企業vs個人事業主など強い立場の交渉者(書籍ではパワープレーヤーと言われている)と「どのように交渉したらいいか?」という部分が気になったので、読んでみました。
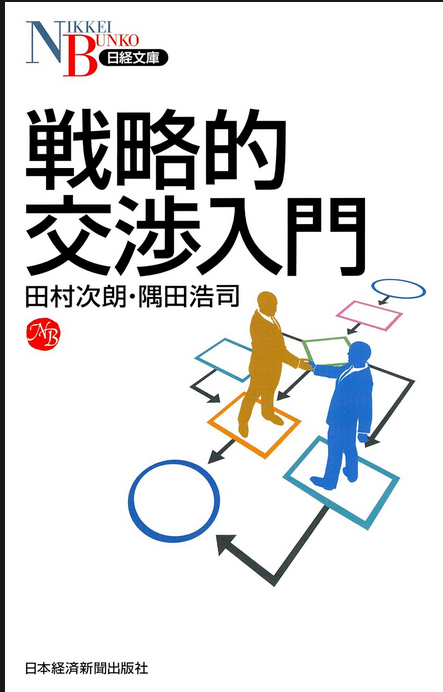
読んでみると、仕事はもちろん日常生活にも使えそうな話でした。
この記事の執筆者が おもしろいと思った部分のみをネタバレありで紹介します。
ただ、書籍にも「入門」とあるので、ある程度の交渉経験がある人などには当たり前すぎて参考にならないかもしれません
この書籍がオススメな人は「これから営業職に就く人」「個人事業主になったばかりの人」「いつも自分にメリットがない合意をしてしまうようなタイプ」「都合良く扱われるタイプ」だね
・よい合意の定義とは?
・交渉は「事前準備」が大事
・合意依存症に陥らないようにすること
・「強い立場」「弱い立場」という考えをやめる
・提案には「根拠」が必要になる→相手に説明させよう
・論理的に正しくても合意しなくてOK
・「会話」と「対話」の違いを理解する
・反論は積極的に行う、察することが美徳はやめよう
よい合意の定義とは?→自分の利益が最大かつ、相手にもメリットがあること


ビジネスの交渉では自分たちの利益が最大限、合意に反映されているかどうかが問われます。
戦略的交渉入門より
合意するだけなら誰でもできますが、交渉できちんと成果を出すということになると、そのためにはかなりの戦略と工夫が必要となるわけです。
よく言われるWin-Win(お互いに得をする)ことかな?とも思ったんですが、書籍ではちょっと違うと書かれています。
大前提が自分たちの利益を最大限にして、相手にもメリットがあること。
つまり、お互いに得はするけど利益が小さくなるのはダメな合意とされています。
書籍では「落としどころ」を見つけるのもNGと言われているね
たしかに その通りですが、後に出てくるパワープレーヤー(強い立場を強調して接してくるタイプ)相手にはどうしたらいいのだろう?という疑問は出ますね
たとえば、大企業から仕事を請け負っている個人事業主(フリーランス)は弱い立場なので、悪条件を飲まなければならないと よく聞きます。
下記の記事で「自分の代わりはいくらでもいる」と、個人事業主である本人も言っていますので↓
https://president.jp/articles/-/92726
※それなりに力がある個人事業主は除く
この記事の執筆者は個人事業主ではないので(ココナラの出品のみ)、完全な予想になってしまいますが‥
良い仕事をする個人事業主ならキチンと交渉すれば、大企業も応じてくれる可能性があるんじゃないかと思っています。
連絡や報告がこまめだったり、ルールの範囲内で修正に心よく応じてくれたり、仕事が早かったり。
大企業でも個人事業主と交渉する専任の担当者がいると思います。
やり取りにリソースが割かれすぎるタイプの個人事業主は、いくら依頼料が安くても避けたいと思うんじゃないでしょうか?
少なくとも この記事の執筆者が大企業の担当者だったら そう思います。
企業で決められた予算はあると思いますが、その範囲内なら一緒に仕事しやすい人に お願いしたい。
※都合の良い個人事業主という意味ではなく、一般的な(日本の)社会常識は持っていてほしいという意味で
なんなら、大企業の担当者が依頼する料金を払うわけではないので、(裁量権があるなら)一緒に仕事をしたいと思える相手を選びたいと自分なら思います。
たとえば、この記事の執筆者が大企業の担当者で 良い仕事をする個人事業主から値上げを打診されたら、せめて自分の上司に相談して値上げを受け入れてくれるように説得まではすると思います。上手くいくかはわからないですが‥(^^;)
交渉の上に、また交渉が出てくるのが面白い
企業内部で交渉を成功させるには、その人(担当者)の「人柄や信頼」も関係ありそうですね‥上司との関係が良好なら値上げ幅にもよりますが、交渉は成功しやすそうです
ともあれ、個人事業主が何かしらの強みを持っている前提なら、大企業の担当者も上司を説得しやすいという話ではありますね。
個人事業は利益を総取りできる代わりに会社員にはない「自己責任」が付くので、そのへんは個人事業主本人に頑張ってもらうしかないですが。
交渉は より多くの情報を持っている者が有利


交渉において「自分の考えが硬直してしまう」との理由から事前準備なしで挑もうとする人がいるらしいです。
ちょっと信じられないね
特に交渉は情報をより多く持ってる方が絶対に有利だと思うし
(マンガやアニメの頭脳戦を見てると‥)
ほかにも、その場その場で考えていたら意思決定に使うリソースが枯渇してしまうと書かれていますね
※人間は物ごとを判断すると脳に負荷がかかります、なので一日に判断できる回数は限られていると言われている
・人間の集中力、忍耐力はストレス状態では短時間で消耗してしまう→ 意思決定の質が低下
・重要なところにだけ集中力を振り分けるには、どうしたらよいかを考える
・考えなくてもいいところはどこかを割り出す
・その場で考える負担を減らすことが大切
・何のために交渉をするのか、合意した結果何を得ることができるのか事前に自問自答しておく
ここで大切なのは本来調べればわかることを調べず、交渉の中で初めて その情報に触れるという事態を避けるということです。
戦略的交渉入門より
なぜなら人間は新しい情報を目にすると、その情報に目がいってしまい他の情報を十分に吟味しなくなる傾向があるからです。
交渉でよりよい合意を得る戦いをしながら、新しい情報のことも考える=マルチタスクをすることになる。
それはミスも増えますね(^^;)
ほかには交渉で重要なことは「論理的思考」と「相手の提案のメリット・デメリット」を批判的に見抜く力が大切だと言われています。
この記事の執筆者はブログをやってるし、節約&倹約家なので買い物をする場面でもメリットとデメリットは常に考えていますね(失敗することもあるけど)
感情で動くタイプや衝動買いしてしまうタイプは、交渉において不利そうだね
「それって、あなたの感想ですよね?」とか「エビデンスやデータは?」と言うと他者から嫌われるらしいですが、交渉を商売にするなら必須の能力ですね。
合意依存症に要注意~より良い合意ができないのなら「決裂」も辞さない


合意依存症の罠が書かれていました、以下は概要です↓
・合意したいという思いを悪用される→希望的観測
・相手の提案に一抹の不安を感じながらも合意したいという思いを抑えることができない
・その結果、私たちは相手の一言にすがりたくなる
・交渉相手が大丈夫だと言っているとか、ここは重要ではないと相手が言っているというように
自分で判断することを回避して相手の言葉に頼ろうとする
・人間の意思決定は全ての選択肢を数値化して、最善の選択をするというような形で行われない
・初めから結論ありきで、それを後押しする一言が欲しいというタイプの意思決定は非常に多い
・自分たちの意思決定のより所が曖昧な交渉相手の一言に依存することがないようにすること
・最後まで合理的な判断を手放さないことが重要
・自分自身は交渉中は冷静さを欠く場合があるのだということを理解すること
これやっちゃうの、人から嫌われたくないってタイプにも多そうだな‥
昔の自分を見ているようです・・(^^;)
(その時の状況にもよりますが)この記事の執筆者は今は人とケンカしてでも自分の意見をハッキリ言えるようになりましたが、以前の自分はこういうことを考えていたのか‥と改めて気づかされました。
「合意」か「譲歩」の2択しかないと視野狭窄に陥っている可能性もありますね、選択肢の中に「交渉決裂」を入れていきましょう
人間は選択肢が2つしかないと思い込むと、判断後に後悔することが多いそうです。
そんな時は選択肢を1つだけ増やしてやると、より良い結果が出る可能性が高くなる(下記書籍も参考になります)↓
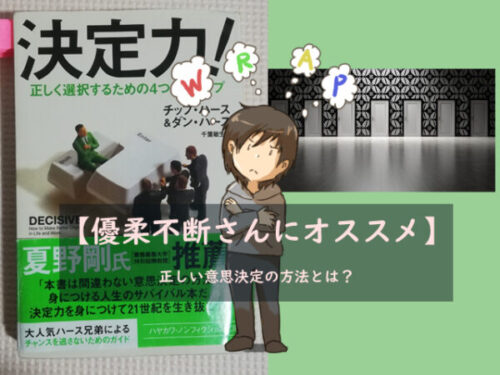
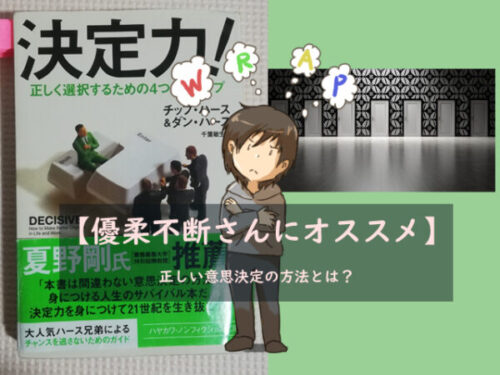
先ほどの個人事業主の例を出せば、自分に強みがない個人事業主は決裂=仕事がなくなる可能性が怖いから、譲歩するしかないと考える。
やはり、決裂しても大丈夫という「何か」が必要ですね。
立場や力に差があるパワープレーヤーとの交渉戦術は、どうしたらいい?


パワープレーとは、交渉相手と自分との関係を強い・弱いという関係でとらえ、自分が強いと思い込むか、強いと見せかけようとする。
「元請けと下請け」「大企業と個人事業主」「医師と患者」「先生と生徒」との交渉はパワープレーに陥りやすい。
ちなみに、弱い立場側から相手は強いと思い込むこともパワープレーと書籍で言われています。
パワープレーヤーの対処法は色々と書かれていますが、特に参考になったのは、
・立証責任→提案の根拠を説明させる
・人間の公正さを逆手取った説明を求める
・・です。くわしくは後述。
パワープレー戦術のデメリットも書かれています。
この強いか、弱いかという二分法が頭を支配すると交渉相手の発言を誤解したり、自分の主張だけを繰り返してしまい、結局、交渉相手との合意のチャンスを逃してしまう。
ほかには、たとえ合意に至っても、どちらかが損をしている=継続的な合意には至らなくなる可能性が出てくるなども指摘されています。
立証責任→提案の根拠を「相手に」説明させる


①ダメな例
客:10%値引きしてください
営業(あなた):できません
客:なぜですか?
※あなたが本来負わなくてもいい立証責任を負っている
②よい例
客:10%値引きしてください
営業(あなた):値引きを提案された理由を教えていただけますか?
※相手に立証責任を問う
法律では ある要求や主張を裁判所に認めてもらうためには、その主張の根拠を立証する責任があります。
戦略的交渉入門より
立証に失敗した場合は その主張は認められないという考え方を立証責任( 証明責任)と言います。
根拠の説明がない要求は拒否して構わない、相手が立証責任を尽くすまで その要求は無視して構わないのです。
したがって、相手の主張の根拠や背景事情は聞いてもいいのではなく、必ず聞くべきなのです。
たとえば、競合他社は このくらいの価格だったとか、サービスが御社より充実している・・というような論理的な(?)立証をされた場合はどうなんだろ?
その場合でも「自分の利益を最大」にするというミッションから離れていれば、合意しなくてもいいそうです。
交渉というのは正しさを証明するところではありません。
戦略的交渉入門より
相手がどれほど正当な主張をしたとしても、こちらに利益がなければ その主張を受け入れる必要はないのです。
交渉相手の説明が理路整然とした場合は、むしろ、こちらも合理的に交渉できる相手だと考えて歓迎すべきです。
悪質クレーマータイプの交渉相手なら合理的な交渉は望めないでしょうしね‥
気の弱い人だと、論理的な立証をされれば合意してしまいそうですね‥(^^;)
ほかには質問されると、つい答えてしまうという話がされていました。
人間は質問されると、答えなければならないと感じます。
しかし、その質問の趣旨がよくわからない場合や その質問に答えると、自分が不利になりそうだと感じた時は相手の質問に対して質問で切り返しても問題にはなりません。
交渉相手の曖昧な主張や要求をまずブロックすることによって、交渉全体を有利に展開することができるようになります。
相手の主張や要求が出されたとき、交渉相手は「理由を説明しただろうか」と自分の中で考えてみることです。
この説明がない場合は相手の立証不足ということになります。
したがって、 即答する必要はないのです。最初から相手の提案に対して、即答しないというルールを決めておくと良いでしょう。
戦略的交渉入門より
自分が確保できる(許容できる)利益の最低額を下回れば、決裂覚悟で はぐらかし作戦に出ると。
ある小さな工場は、利益にならない&手間のかかる仕事ばかり取ってきた営業に社長が愚痴っていたな
立証責任の転嫁に気をつける
先ほどの10%値引きを要求してきた客と営業(あなた)の別バージョン。
客:10%値引きしてください
営業(あなた):では5%値引きで、どうでしょう?
客:なぜ10%ではダメなんですか?
※立証責任の転嫁が起こっている
YESといえば、全面的な譲歩=あなたの損。NOといえば相手からNOの理由について説明を求められる。
相手は自らの主張の理由を十分に説明していないのに、こちらはNOである理由を説明しなければならない。
立証責任が転換されてしまったという話です。
まず半分の5%は譲歩している。この部分は全面的な譲歩ではないにせよ、利益を放棄している。
さらに残りの5%はNOと言っているので「なぜ残りの5%はダメなのか?」と相手から質問され、その理由を説明することになってしまう。
このような二分法(二択)に陥りそうな問いかけには、まともに答えないというのが最善策ということになります。
この場合は、前述している選択肢を1つ増やす方法はダメそうですね(選択肢3つ→10%値引き・5%値引き・値引きはNG)
あと、簡単に5%でも値引きしてくれる相手だと思われるのもよくないよね、値引ありきの価格設定なのかと疑われるという理由で
家電量販でよくある話ですが、高値で表示して交渉した客だけ値引きされるとか。
※家電量販店での交渉は、事前に最安値を調べて店員に提示する必要があります
値引き前提の価格表示だと相手に悟られてしまうと、信用をなくす場合もありそうですね。この人(会社)は高値で吹っかけると。
たとえ、値引き前提の価格提示だとしても値引き案を出し渋るような「演技」は必要かもしれません。
交渉者は、つねに交渉相手に対して過大評価している傾向があるそうです。
交渉相手も不安を持ちながら交渉しているのだという事実を忘れてはいけません。
たとえ、本人たちが強い立場・弱い立場と思っていてもですね。
アンカリング(事前に提案された数字)の罠に気をつけよう
アンカリングの例は、事前に提案された数字を基準に考えてしまうことです。
例えば、フリマアプリで物を売るとき・・
・5000円で売り出す
・4000円まで値下げできませんか?という依頼が来る
・この出品者の中で「4000円」という値段が基準になってしまうことをアンカリング効果という
・はやく物を売りたい人はOKするか、前述している例と同じく「4500円でどうでしょうか?」と提案する確率が高くなる
・たとえ、相場価格が4800円であっても
書籍ではアンカリングの効果を多少なりとも回避するためには、アンカリングという概念を知ることと提唱されています。
アンカリングという概念を知っていれば相手からの価格表示に警戒して、受け取ることができる。
書籍の後の方で出てきますが、値段の幅の設定が大事です。
相場や自分の手取りを考えて、定価~〇%までしか値下げしないと予め決めておくこと。
フリマアプリって、金額は言わず「値下げできますか?」とだけコメントが来ることもあるよね
先ほどの家電量販店と似た話ですが‥
感覚的な表現を聞いただけで譲歩してしまうならば、交渉相手は詳細な説明をする必要がなくなります。
戦略的交渉入門より
このような交渉を安易に続けていると、次第にこの人は詳しい説明をしなくても譲歩してくれる人だという評価をされてしまいます。
つまり、舐められるということですね(^^;)
人間関係や仕事において、他者から「舐められる」というのは本人に不利益が大きいので、できるだけ避けなければならない。
雰囲気を壊したくないという思い
書籍では「会話」と「対話」の違いが紹介されていました。
会話:お互いのことを知るためにコミュニケーションを取ること、明確な目的やゴールがない
対話:お互いの意見の相違があることを前提とするコミュニケーション、自分たちの意見を開示して、お互いに納得いくまで議論を重ねること
対話は、どちらか一方の意見に屈服するのではなく、長所や短所を踏まえながら最終的には お互いの意見の相違を克服すること。新しい価値・アイディア・発想を見出していくこと・・とあります。
交渉というのは、会話ではなく対話です。
お互いの意見が違っていて当たり前・・という対話の基本原則を忘れてはいけない。
各国の代表が互いに対談(対話)する前に、仲良く?会話したり食事したりするけど、逆効果にならないんだろうかね‥?
国の代表みたいな人はプロだから大丈夫なんでしょうけど、この記事の執筆者のような良い相手には強く出れないタイプには事前の会話は逆効果になりそうです(^^;)相手は好都合でしょうけど。
相手の人柄や雰囲気に釣られない・流されない訓練を積めば大丈夫ですかね‥たぶん・・
書籍には、パワープレーヤーの意見をできるだけ理解しようとするが、譲歩はしないというスタイルを維持することに全神経を集中させましょうと提案されています。
自分が弱い立場であったとしても、舐められずに信頼関係を結ぶのは これしかないですよね(^^;)
人間の「公正さ」を逆手取った説明を求める


例えば、パワープレーヤーから不利な合意を求められたときに有効と言われています。
ちょっと長いですが引用↓
あなたのご提案を受け入れた場合、最終的にどのような合意内容になるか教えていただけませんか?といった質問は効果的です。
戦略的交渉入門より
人間は自分は他人よりも公正であると考えています。
理不尽な仕打ちをするパワープレーヤーであっても案外自分は公正な人間であり、自分の主張は交渉相手にとっても公正なものだと思っているものなのです。
したがって、交渉相手に著しく不利な帰結をもたらす結果になることをそのままはっきり伝えること、それを自分自身で説明することには多少の抵抗があります。
しかし、あえてその説明を求めることによって、パワープレイヤーの主張が こちらにとって受け入れがたいものであることを相手に気づかせることができるのです。
つまり、交渉者と相手に どんな利益やメリットがあるのか?を相手に説明させるという感じですね。
理不尽な仕打ちをするパワープレーヤーであっても案外自分は公正な人間であり、自分の主張は交渉相手にとっても公正なものだと思っているもの
>典型的な認知が歪んでいるタイプか、想像力が足りない人には通用しそうだね
不公正承知なパワープレーヤー(サイコパス?テイカー?)には通用しなさそうな手法ですけどね
おそらく、サイコパスみたいなパワープレーヤーは少数派でしょうし、交渉関係の仕事だけじゃなく、プライベートでも使えそうな質問です(^^)
想像力が足りない人は要注意?相手をモンスター化しない
サイコパス系のパワープレーヤーは別ですが‥交渉相手をモンスター化するとビジネスパートナーではなく「敵」とみなすようになる。敵とみなすと交渉が難しくなる。
交渉相手のモンスター化が起こりやすい状態が紹介されています↓
相手のモンスター化は交渉相手のごく一部の行動や仕草、表情といったものを深読みしすぎるか、勝手な思い込みが強すぎる場合に発生しやすくなります。
戦略的交渉入門より
むしろ、相手のモンスター化現象は交渉相手の表情をじっくり観察することによって作られるのではなく、交渉相手をほとんど観察せず、自分の勝手な思い込みで幻想を作り上げているだけなのです。
書籍では、相手の「発言内容だけ」に集中して、楽天的&悲観的な思い込みを排除せよと言われているね
頻繁に この手の被害妄想(?)を聞かされている身としては、すごく納得できる話。
しかも、本人は自分の都合のいいようにしか解釈しない、都合の悪いことは見ない。
信頼できる第三者が都合の悪い部分を指摘して、本人に考えさせる作業の繰り返しです‥_(:3 」∠)_
・・と偉そうにいう自分も心に余裕がなくなると、被害妄想マンに陥る可能性が高いので気を付けようと思いました(できれば信頼できて、指摘してくれる第三者がいると助かる)
意外と盲点?交渉決裂のメリットを考える
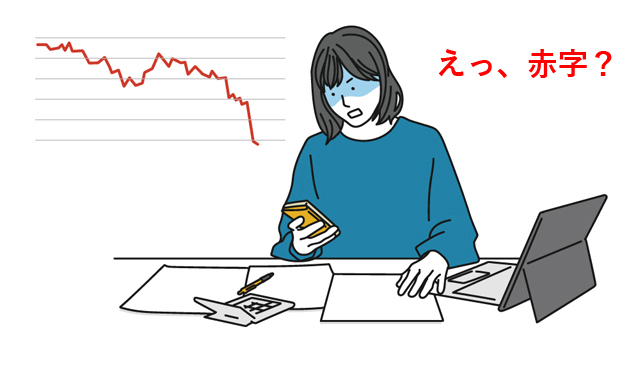
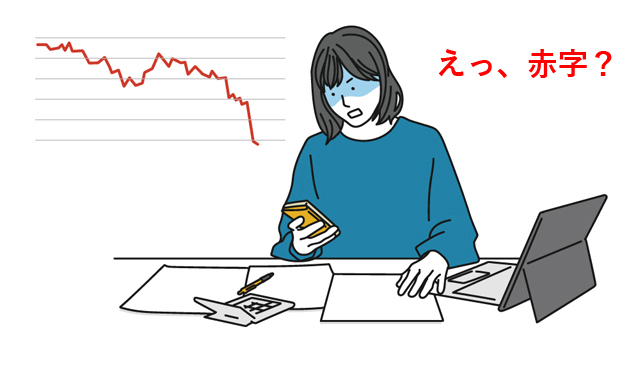
交渉決裂は悪いことと とらえる人も多いと思いますが、ここでは「交渉決裂時のメリットを考えよう!」と言われています。
交渉決裂のメリットを考えるには、初心や基本に戻る必要があります。
・交渉が決裂したら、代替的な調達先は本当に存在しないのか?
・この部品を必ず使わなければいけないのか?別のもので代替できないか?
・そもそも、この製品を作るのをやめてしまった方が会社の利益になるのではないか?
・「問題」を冷静に分析するスタートラインに立つ
前に読んだマーケティング系書籍ドリルを売るには穴を売れの「お客さんはドリルが欲しいのではなく、穴を空けたいのだ」という話と似たようなものですね。
上記の例ような部品関係なら、部品どうこうより「完成品」が問題なくできればいいわけだよね?
さらに、その「完成品が会社の利益に寄与しているのか?」を検討する必要も出てきますね
会社としての本質は、
・今まで作っていたものを製造したい×
・自分たちの利益が最大限になるものを製造したい(取り扱いたい)〇
・・ですよね。
利益が大した出てないものは交渉を決裂させて、作る&取り扱いをスッパリやめてしまうという手段も取れます。
これは普段から物ごとのメリット・デメリットを考えている人は得意そうな分野ですね(^^)
もちろん、「盲点」みたいなものは必ず発生するので、信頼できて指摘してくれる第三者の存在があると助かると思いますが。
※悪質コンサルに要注意という話でもあります
恐怖そのものに恐怖する性質と楽観視しすぎる性質に対処する


私たちは恐怖そのものに恐怖するという性質があります。
戦略的交渉入門より
恐怖が見えなければ見えないほど、その不安は高まります。
悪い方向に考え出すと止まらないやつ
でも自分の場合、悪い方向(悲観的)寄りに考えていた方が期待せずに済むので、いつも悲観寄りの思考をするクセがありますね
悲観的すぎるのもダメだし、楽観的すぎるのもダメ。
この記事の執筆者の経験上、10:0か0:10じゃなければOKとしています。
書籍内では‥
最悪、この取引がなくなったら、うちの会社は潰れるのかどうかと考えてみるのが良いとされています。
もし、そこまで酷くないのであれば何か打ち手はあるはず。
対策を考えるときは、あいまいではなく具体的に「どうダメなのか?」を考えることとされています。
・大切な取引相手との取引を失ったら大変なことになる、困ってしまう×
・代わりの取引先を探すのに最大1か月はかかる、その間どうする?〇
上記が例えば、あなたが個人事業をやっていて大切な取引先がムチャな継続的値引きを要求してくる。あなたは断りたいとします。
断ったことで取引先と契約打ち切りになる→新しい取引先(≒継続的な依頼者)が見るかるまで、生活費分を稼げるバイトや日雇いをするという対策が浮かびます。
余談ですが‥
前の方で紹介した「決定力!」という書籍には逆パターン、つまり楽観しすぎる時の対策が書かれています。
事前検屍をするという章で計画を実行する前に「あなた計画は失敗しました、原因は何だったでしょうか?」と失敗要因をできるだけ考え出すというもの。
事前検屍をすれば、楽観視しすぎず冷静に計画の障害になりそうなものが見えてきます。
※交渉の場では、「計画」→「交渉」に置き換えてください
戦略的交渉入門の書籍では後半に、事前検屍と似た効果を持つ「悪魔の代理人」の話が紹介されています。
悪魔の代理人は提案者の案に直接、欠点の指摘や批判をするので提案者の人格否定と とらえられかねないので注意が必要です。
ほかには反論は すべてホワイトボードに書き、本人たちに人格否定だと感じさせない策も有効さとされています。
これらのことを考えると、「準備する時間がない=判断する時間が短い」というのは結構なデメリットになり得そうですね(^^;)
時間が無限湧きするわけでもないし、他にもたくさんの仕事を抱えてる可能性がある、早めに決めたいと思う交渉者も多いよね
失敗すると致命傷を負いそうな交渉の場合は慎重になった方が良さそうです。
準備する時間がない場合は、その場では重要な判断をしないことにするなどの独自ルールが必要。
準備時間の確保が難しい緊急を要する交渉の場合(緊急修理や災害、急な引っ越しなど)は、多少の交渉の甘さ覚悟で、時間の許すかぎりの準備しかできませんがね‥(^^;)
心理戦術を使う&使われた場合は気を付けよう


心理戦術とは何か?
「ひとことで言えば、交渉相手を合理的な思考から遠ざけ、短絡的な結論に陥るように誘導するテクニック」
・・と紹介されています。
素人相手(客など)には通用しそうだけど、プロの交渉人やベテラン営業には通用しなさそうなテクニックだよね
プロ相手に心理戦術を使ったら、むしろ関係が悪くなりそうですね(お客さん相手でも後から、はめられたと気づかれたら心象は悪くなる可能性が高い)
スポーツ等の何らかの正式な試合でみる心理戦やフィクションの心理戦の話は結構面白いけど、社会生活でやるには注意が必要かもしれませんね。
書籍では有名な心理戦術である「フットインザドア」と「おねだり戦術」が紹介されていました。
フットインザドア戦術・・最初に小さい要求を呑ませていき、気づかない内に大きな要求を呑ませる戦術。
例:パソコンを買うときに店員から無料の○○サービスを付けますか?→YES、月額100円で動画見放題の有料△△サービスを付けますか?→YES、月額4000円の光回線に乗り換えませんか→YES・・と続いていく。
おねだり戦術・・合意の直前や直後を狙って追加条件を提示して、相手に飲ませてしまう戦術。
例:この内容で合意となりますが、少しだけ費用を追加して便利なオプションを付けませんか?など。
合意寸前あるいは合意してすぐという状態は、最も緊張感がなくなる危険な時間だそうです。
あとは、メリットと一緒にデメリットを説明しない交渉相手は信用すべきではないと言われていますね。
このブログでも、↑部分は気を付けています(^^;)
反論や批判が出なかった場合は、いったん疑いの目を持つこと


「私たちの合意内容には必ず、ほかの合意の可能性が存在する」
しかし、 ほとんどの人たちは この他の合意の可能性があることを忘れ、現在の合意案が最適であると考えがち。交渉ではお互いの中での合意内容に唯一の正解などはない‥と書籍で指摘されています。
前の方でも言ってるけど切羽詰まってくると視野狭窄(しやきょうさく)、つまり選択肢が2つしかないと考えがちだよね
視野狭窄の対処法として、書籍で このようなことが言われています↓
ある意見に対して反論や批判が出なかった場合には、その意見を直ちに採用することを避けるというルールを決めることです。
戦略的交渉入門
(中略)
必ず どのようなプランでも何らかのリスクや欠陥もしくは反論の余地が残されています。
そのような問題が議論されないまま採用されるという状態は、すでに集団極性化が発生している疑いがあるのです。
集団極性化の意味↓
集団で意思決定を行う際、個々人の当初の判断や行動傾向、感情などが、集団でのさまざまなやりとりを通す中で、極端な方向に強くなる現象を集団極性化と言います。
心理学用語サイコタムより引用
https://psychoterm.jp/basic/society/group-polarization
イエスマンだけで組織をかためてしまうと、集団極性化に陥りやすそうですね(^^;)
あとは上の立場の人(役員クラス)の意志決定力が強すぎると、下の立場(平や中間管理職)が何も言えなくなったり。
【心理学?】口に出すかは別として、自分の感情を押し殺してはいけない理由


いっけん、交渉術とは関係がなさそうな心理学的なことが書かれて、その通りだなぁと印象に残っています。
「感情を自己認識することが大事」
以下、概要↓
・相手の発言よりも自分の発言に対して自分がどう思ったかに焦点を合わせる
・大事なのは自分の感情を抑制してはいけないということ
・対立や摩擦に直面したとき、冷静さを失って感情的になることもある
・その感情を抑え込まなければならない、なんとか冷静に対処しなければと思えば思うほど感情は自分の中で荒れ狂う
・感情を止めることは不自然で、そもそも不可能
・感情を押し殺そうとすればするほど、相手に対する批判に繋がる
・たとえば、あの人は性格が悪いとか、私のことを無能だと思っているのではないか
・といった具合に相手に対する悪い印象や不快感を評価につなげてしまう
・悲観的な思考構造から抜け出して、冷静に対処するためには自分が感情的になっていることを自己認識することが重要
自分の感情を抑制するのが当たり前の親族と長年接してきて、自分も染まっていましたが全部上記に当てはまっている・・(^^;)
悪口モンスターは こうやって作られるのかと。
自分もそうでしたが、認知が歪むと矯正には結構な時間がかかる。
前に認知が歪むことのデメリットを以下の書籍(記事)で学びましたが、認知さえ歪んでいなかったら、または歪みを正す意志があるなら、いくらでも再起が可能である↓
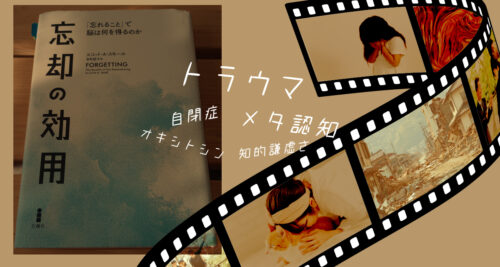
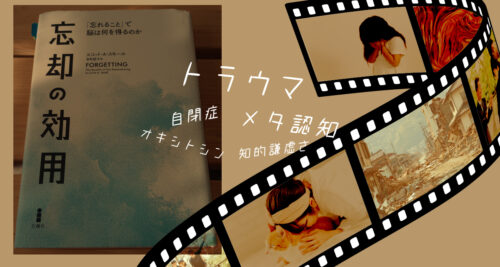
自己責任で自分の欲望に忠実な人の方が人生が楽しそうに見えるのは このためか‥
口や態度に出すかは別として、ドス黒い感情でも「いま自分は こう感じている」を自己認識する必要があるってことですね
ワーキングメモリが小さい この記事の執筆者は自分の考えを保ちつつ、口や態度は真逆なことをする‥という器用なことができないので、口に出したらマズそうなことは沈黙&ノーコメントを使いこなしています。
冗談や遊び(創作活動ふくむ)ならともかく、嘘をつくというのは心にかなりの負担がかかるということでもありますしね。
※プロ俳優とか一部の天才Vtuberなどは除く
前にレビューしたギャルゲー(フィクションの話ですが‥)でも、自分の気持ちを押し殺していたキャラは全員病んでいましたしね↓


交渉学では、こんな感じに自己認識すると良いそうです↓
「いま交渉相手が無理な要求をしているので、不快な思いをしている」
認知が歪みだすと以下のようなことが起きます↓
感情の自己認識を怠ると感情から生まれた印象が次第に確信に変わり、最終的には偏見にと固定されていきます。
戦略的交渉入門より
「こんな無理な要求をする相手は人間的に卑しい人間であるに違いない」というような決めつけです。
感情は自己認識することができますが、自分の中の偏見を自己認識するのは はるかに難しいのです。
自分の感情を抑えずに自己認識すること、そこから感情による負の側面を克服することができる
「この人なんでこんな偏見(しかも大体間違ってる)を持ってるんだろ?」って人間は結構上記に当てはまってそうだね
感情をコントロールできない人→偏見が強い人(または演技ができない人)は交渉に向いてないのかもしれませんね
世間的には あまり褒められた職業じゃないのかもしれませんが‥キャバクラやホストは感情労働の代表例ですよね。
よほど向いてる人・失うものがない無敵な人じゃないと、すぐに病んでしまいそう‥(^^;)
余談ですが‥
この記事の執筆者は若いころ、舐められてもヘラヘラ笑う訓練をして世の中を渡ってきました。
ある時期から「それは違うよなぁ(。-`ω-)」という怒りから、イラっとした感情を正直に そのまま口や顔に出す方向にシフトしていきました。
相手とケンカに発展することも何回かありましたが、舐めてくる人間の数は激減しましたね。コイツは危険だと思われて丁重に扱われたり。
現在は心が病むこともなく、快適に過ごせています(^^)
Xでも似たようなことをポストしていました↓
自分を変えるには「勇気」も必要。
世の中には努力や我慢はできる人が、勇気を出せない人が多いのだとか。
交渉が上手くいかない原因は「自分」の中にも存在する?


交渉相手との対立を強める原因は交渉相手ではなく、自分自身の中にもあると書籍で指摘されています。
先ほどの偏見とは別のことです。
・交渉相手に対する過剰な期待
・交渉相手は誠実に交渉すべきであるという期待がその代表例
・それ以外にも、時間通りに来るべきであるとか
・プレゼンテーションの資料はちゃんとカラーで印刷すべきであるといった些細な問題から
・私の提案は正当なのだから受け入れるべきである
・などの押しつけがましい期待まで、私たちはいつも 交渉相手に色々なことを期待する
・当然ながら この期待を裏切られると腹が立つ
・この相手に対する期待値が対立の原因になる
期待値って、どれくらいまで下げるのが正解なんだろうか?
非交渉の話で、この記事の執筆者の経験談ですが‥ある作業で、作業はすべて一人でこなすくらいの予定で計画を立てた方がストレスが激減しましたね(本来は必ず手伝いが入る)。
交渉だと、頑固な高齢者・反抗期くらいの子・言葉の通じない宇宙人(?)との交渉を想定すれば、ストレスが激減するのかもしれません。
【察してくれは通用しない】言葉によるコミュニケーションをサボらないこと


※ここでは「言葉によるコミュニケーション≒交渉」とします
私たちは交渉によって問題を解決することよりもむしろ、交渉することなく自分たちが努力すること、たとえば、「多くを語らず黙々とやるべきことを実行する」ほうが好ましいという発想にとらわれてしまうことがある
戦略的交渉入門より
(中略)
日本人は多くを語らないこと、言葉ではなく態度で示すことを重視するあまり、言葉を使って自分の立場を主張したり、相手の提案に意見や質問をしたりすること、それ自体を潔しとしない傾向があります。
交渉で一番重要なのは こちらの考えを伝え、相手の意見を聞き、そこで議論することだと書籍で言われています。
「察すること」と「言葉によるコミュニケーション」の両方ができる上で、有利になると判断して「察する」を選んでいる場合はいいけど、多くの人は言葉によるコミュニケーションをサボってる(または出来ない)だけに思えるんだよね
相手にいうことを聞かせる手っ取り早い方法は「暴力・非暴力の制裁・無言の圧力」のどれかですからね
パワープレーも似たような感じか‥
言葉によるコミュニケーション≒交渉は「根気」「細かい知識」「言語化能力」「相手の話に耳を傾ける」など色んなもの・能力が必要になってくる。
さらに、この記事の執筆者みたいに時々ケンカに発展することもあるので気力も使う。
つまり、超大変だということ。
・察することが美徳×
・察し+言葉によるコミュニケーションの両方を使いこなす〇
※前の方で出てきた感情を押し殺しすぎて(≒察しすぎて)、相手に偏見を持つ話ともつながっていますね
この記事の執筆者も訓練中の身ですが‥相手の考えを察しつつも、あえて自分の考えを優先する行動をとっています(ただし時と場合にもよる)。
それくらい極端にやらないと、自分を変えられないと思うので。
いまは極端にやっていますが、色々と腹落ちしたら適宜調整を行うつもりです。柔軟性も大事だと思うので。
さらに言葉によるコミュニケーションは「勇気」も必要
書籍では国際的な交渉(外国人との交渉)の話がされていました。
海外は日本と文化や習慣が違うので、さらに大変になります。
・一般に国際的な交渉では反応しないことは認めたことになってしまう
・さらに1回だけの反論では反論しているとは見なされない
・自らの立場を守るためには言葉による闘争を挑む必要がある
察して「我慢」するより、言葉で戦う方が勇気がいりますしね(^^;)
逆に、想像力が足りないため(?)言葉での対立が多い人は、「想像力≒察する能力」が必要になってくる。
とにかく、「察する能力(想像力)+言葉によるコミュニケーション能力」の両方を使いこなすことが大事って話ですね
札束でブン殴るも有効かも?
記憶があいまいで申し訳ないんですが‥
まえに何かの記事で、日本で商売していた人が海外で商売展開して、現地スタッフを雇うときに国の文化や習慣の違いで苦労した話がありました。
(どこの国かは忘れましたが)現地スタッフの人たちは約束を守らないのが当たり前で、ドタキャンからマネージャーの伝達ミス→ショーの当日に物がない・人がいない‥で血の気が引いた事態になった話など、日本では考えられない話がてんこ盛りでした(^^;)
上記の例だと、バイトに相場より高い給料を提示+後払いが有効なんだろうか?
それプラス、仕事の出来がよかったらチップを払うのもいいかもしれませんね
マネーパワーも有効なのかも?という話。
まとめ:交渉術は日常生活でも使える心理学


・まず「自分の利益は最大限になっているか?」を考える
・自分が得をするなら交渉決裂も視野に入れる
・合意依存症には要注意!
・不利な条件を提示されたら、立証責任を相手に問おう
・自分の不快な感情を押し殺してはいけない
・言葉によるコミュニケーションと察する能力の両方を使いこなそう
日常生活で当たり前にやってることも多かったですが、書籍で言語化されていて より理解が深まりました。
すでにベテランの域に達しているような人には向かない書籍ですが、交渉になれていない若い人、これから営業職に就こうと思っている人、気の弱い人にオススメな書籍です。
書評・レビューランキング
にほんブログ村