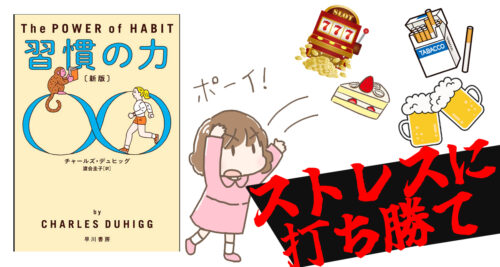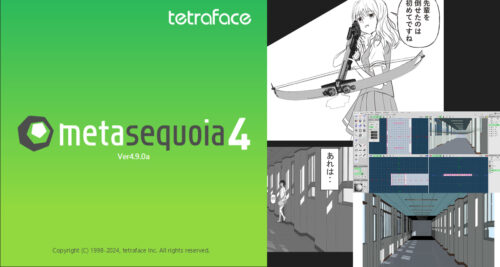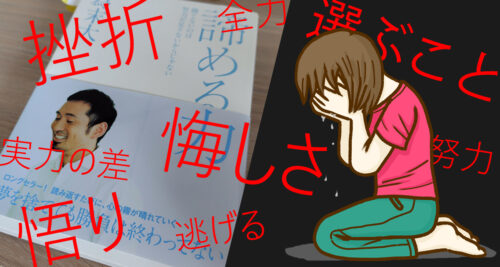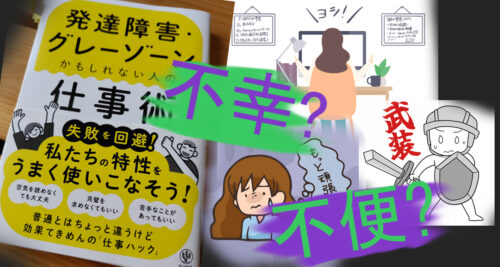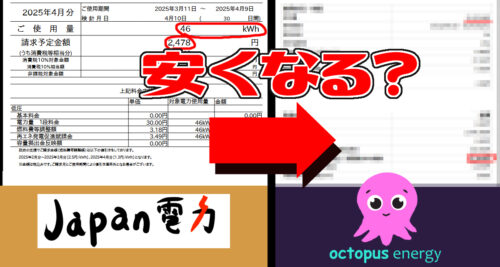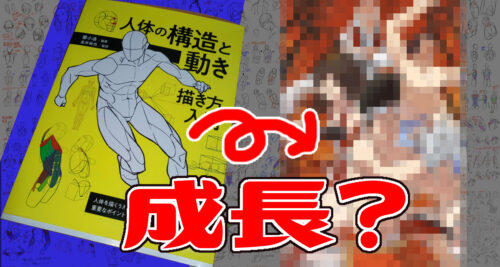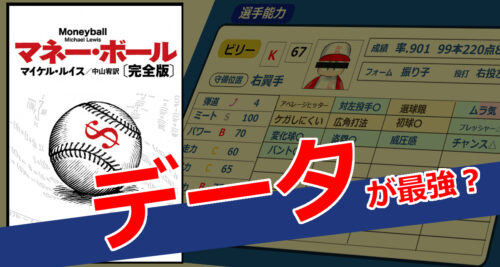・ずっとダイエットに失敗していた人が急に成功する
・弱小スポーツチームが、考えなくても動けるように訓練したら強豪に
・ギャンブルやニコチン中毒、アルコール依存症になってしまう仕組みとは?
・人々の行動を統計分析して来店してもらう手法
・認知症だけど昔のことは覚えている
上記の例は全部人々の「習慣の力」によって、変化がもたらされたと紹介されています。
「習慣の力」という書籍を読みました↓
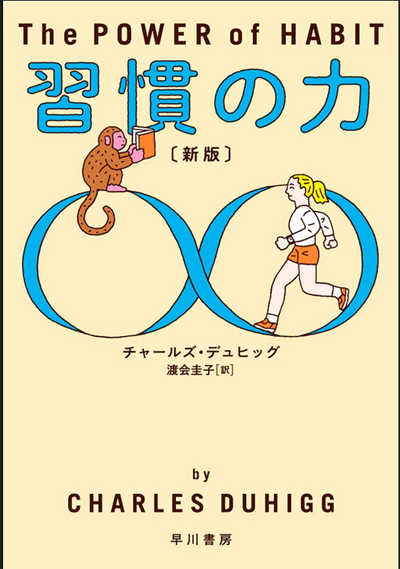
この書籍は「中毒や依存症から脱出したい!」「自分を変えたい!」と思ってる方にオススメな書籍だと思いました。
書籍の内容全部は実行できなくても、何らかのヒントになると思います。
・習慣=きっかけ→ルーチン→報酬
・習慣があるから脳は休める?
・習慣を変える→「きっかけと報酬」は今までと同じものを使いルーチンを変える
・ニコチンやアルコールなどの依存症から抜け出すためにやること
・歯磨き習慣のなかった国に歯磨き粉を売った手法(マーケティング視点)
・スポーツにおける達人のスランプは習慣に従わないことから起こる?
・ヒットしなかった良い曲をヒット曲に変える方法
・悪い習慣を断ち切り、良い習慣を根付かせる
・その他、面白かった余談など
この記事の執筆者が気になった部分のみネタバレありで紹介します。
習慣=「きっかけ→ルーチン→報酬」である

「習慣とは何か?」わかりやすい例として空腹時の行動。
きっかけ:空腹
ルーチン:食事
報酬:空腹を満たす
↓
さらに、毎日同じ時間に同じものを食べてるような人だと・・
きっかけ:朝7時
ルーチン:いつものパンを食べる
報酬:空腹を満たす?満足感?
お腹がすいてなくても朝7時になると、いつものパンを食べたくなる。これが「習慣」と書籍で言われています。
さらに1つの習慣を変えると、ほかの習慣も変わるそうです。根っこの習慣をキーストーンハビットという。
書籍で紹介されていた女性は、離婚で精神を病んで体重が増加→ダイエット→マラソンで運動習慣ができた→生活のリズムが良くなったそうです。
この習慣というのは以前読んだ「影響力の武器」や「スイッチ!」「ファスト&スロー」にも書かれていた話だね
それぞれ、習慣≒自動操縦(影響力の武器)やら、習慣≒速い思考(ファスト&スロー)などと言われていましたね
対極にあるのが、頭を使う≒手動操縦(影響力の武器)と論理的な思考≒ゆっくりな思考。
ファスト&スローは内容が若干難しいので、内容が似ている「スイッチ!」が個人的にオススメ↓
ラットの実験からわかる「習慣の力」を使いつづけるメリットとデメリット


書籍でラットにチョコレートを与える実験が紹介されていました。
条件など↓
・実験中、ラットの脳の活動を調べる
・迷路の「決まったところに」報酬のチョコレートを置き、ラットを迷路に放つ
・チョコレートに辿り着けばチョコレートを食べてOK
・この実験を同じラットで何度も繰り返す
結果↓
・最初の数回、ラットは迷路をさまよったり、壁を引っかいたり、チョコレートの匂いを頼りに歩き回る
・ラットは回数を重ねるごとに、ゴールにたどり着くまでの時間もどんどん短くなった
・次第に匂いを嗅ぐのをやめ、曲がる方向を間違えることも減った
・迷路の道筋を覚えるにつれて、ラットの脳の活動は低下する(無意識の行動になる)
・つまり新しい情報をキャッチして処理する脳部位の機能が低下する
・脳の基底核という部分は、脳のほかの部位が眠っている時でも習慣を保持する
・・というような結果が示されています。
つまり習慣ばかり使いつづけると、新しい情報をキャッチして処理する能力が衰える可能性があるということ。これがデメリット。
メリットは労力の節約になること。
・習慣が形成されるのは脳が常に楽をしようとするから
・脳は決まった手順を何でも習慣にしてしまおうとする、その方が労力を節約できるから
・歩く、食べものを選ぶといった基本的な行動について、常に考えていなくても平気になる
・そのため、脳のエネルギーを新しい商品発明、新しい分野の勉強に注ぐことができる
・習慣のループがなければ毎日の生活で起こる幾多の些細なことに押しつぶされ、脳は疲労し、活動を停止してしまう
あと、怪我や病気で基底核(習慣をつかさどっている部位)が損傷した人間は、頭脳活動が麻痺してしまうことが多いそうです。
基底核にダメージを受けた患者は、ドアを開けるとか、何かを食べるとか、基本的な行動にさえ支障をきたす。
これは重要でない些細な事を無視するという能力を失ってしまうから。
ある研究で基底核が損傷した患者は、恐怖や嫌悪といった人の顔の表情を認識できないことが示されている。
顔のどの部分を注意してみればいいのか、よくわからないから。
だから基底核がないと、私たちが毎日頼っている、何百という習慣を利用できなくなる。
前に読んだ「忘却の効用」にも書かれていたね
たしか自閉症の特性が これに当たるとか
ほんの少し違うだけでも新しい情報と脳が認識して疲れたり、物事を要約する力や要点だけを取り上げる力がないので、認知の混乱が起きる・・という話でしたね
ほかには「習慣の力」には短期記憶が弱い認知症の例が紹介されていました。
認知症患者は新しい情報は吸収しにくいが、反復行動を繰り返すことで習慣が生まれ、反復行動をした新しい情報に関しては覚えられるという話。
たとえば、今まで住んでいた場所から引っ越し→新居→近所の公園→新居→近所の公園・・を何度も行き来すれば認知症患者でも新居から近所の公園までの道のりは覚えられる≒習慣化する。
しかし、近所を歩き回ってるときにいつもの道に何か変化があったら、途端に迷ってしまう。
道路の補修工事をしていたり、暴風で並木の枝が吹き飛ばされていて、いつもと見えるものが変わってしまうと近所でも迷子になってしまう。
おそらく、雪が降るような地域だと夏と冬でも迷ってしまいそうですね・・(^^;
忘却の効用でもいわれていましたが、習慣は「融通が利かない」「ちょっとしたことで習慣が崩れてしまう」という点もデメリットかもしれません。
抑えられない衝動・欲求は、どのように来るのか?


習慣=きっかけ→ルーチン→報酬・・という仕組み。
つまり、何か「きっかけ」があり「報酬」を期待して、「ルーチン」を行う仕組みになっています。
喫煙者の例
きっかけ:タバコを見る
報酬:脳がニコチンを期待し始める
ルーチン:タバコを吸う
喫煙者はタバコを目にするだけで、喫煙者の脳はニコチンを求めてしまう。
それが得られないと欲求は膨れ上がり、喫煙者は無意識にタバコに手を伸ばすことになる。
ついついメールを確認してしまう人も同じ原理。
対処法としては衝動を消して「きっかけ」さえ取り除けば、受信箱を確認しようと思うこともなく、ずっと働くことができるそうです。難しそうですが・・(^^;
テーブルの上にチキンやフライドポテトが置いてあるのを見ると、たとえ腹が空いていなくても脳がその食べ物を期待してしまう。脳が求めてしまうんです。
習慣の力より
正直に言うなら、そもそもそういう食べ物を好きでもないのに突然その欲求に抗えなくなる。
そして、食べた途端に欲求が満たされた喜びに包まれる。屈辱的ですが習慣とはそういうものです。
自分も仕事中は何かを食べる気が起きないんですが、家にいると ついつい何か つまんでしまうので身に覚えがありすぎる
ただし、良い習慣というのも同じ仕組みで起きているので、悪い習慣を良い習慣に変えましょうと書籍で提案されています。
例・・
・仕事に励むのは何かを達成したい、自尊心を満たしたいという欲求から来てる
・運動するのは爽やかな気分を味わいたいという欲求から来てる
これらの欲求(書籍でいうところの報酬)は本人が認識できてない場合が多いので、探し出して対処していかなくてはならないと言われているね
「きっかけ」と「報酬」を探す方法は後述します。
歯磨き習慣のなかった国に、歯磨き粉を売った方法とは?(マーケティング視点)
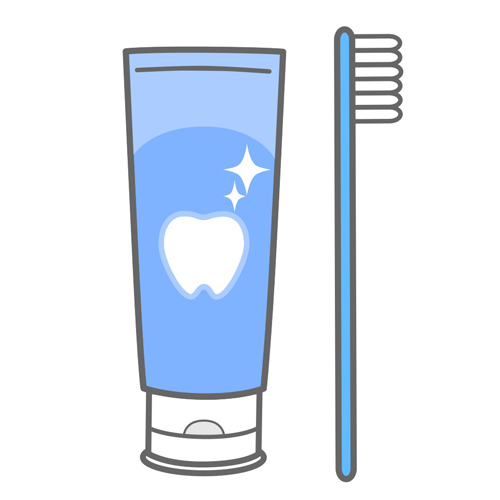
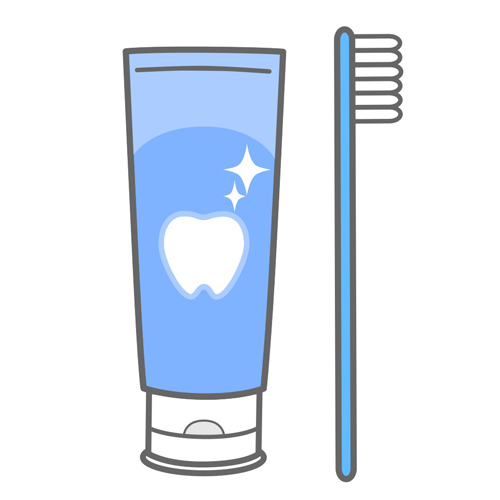
米国では過去、国民に歯磨き習慣がなかったため虫歯で苦しむ人が多かったそうです。
加えて、商品広告のスペシャリストが練り歯磨き粉(ペプソデント)を流行らせるために行った対策などが紹介されていました。
ペプソデントを流行らせたのは・・
・美しい白い歯を手に入れるという広告×
・歯がキレイになった「気がする」という感覚〇
ペプソデントの歯磨き粉に ひんやり・ピリピリする後味(ミント系?)を加えることで、それを使った人たちが歯がキレイになった「感覚に」なり、ペプソデントは売れたそうです。
コレわかるなぁ
歯なんて専門家が専用の機械を使ってチェックしないと、商品を使ったことによる効果なんてわからないからね
「やった気になる感覚」って大事だね
素人相手への商売なら、なんとなくの感覚・雰囲気を売るのは大事ですね
この記事の執筆者は ちゃんとした結果が欲しいですが・・(^^;
あとは虫歯で痛い思いをした人が、歯磨きを習慣化したというパターンもありますね。
余談:最初はまったく売れなかったファブリーズを世界に広めた戦略


今では世界で売れてるファブリーズ(消臭・除菌剤)のことが紹介されていました。
ファブリーズがはじめて売り出されたころ、「消臭と除菌剤」という効果を押し出して売っていたそうです。
しかし、まったく売れなかった。
そこで少ない顧客の中でもファブリーズを愛用している人のもとへ行き、調査を行った。
すると、ファブリーズを愛用していた顧客は掃除後の仕上げに爽やかな香り付けとしてファブリーズを使用していたそうです。
つまり、消臭や除菌目的ではなく、掃除後の「ご褒美として」ファブリーズを使っていたということ。
その後、「掃除後の仕上げ」「香り」を前面に押し出して売り出したところ大ヒットを記録した。
これも、
・自分の家の匂いは住人にはわからない=消臭と言われてもピンとこない
・菌は目には見えない=除菌の効果がわからない
・・って所から来ていますね。
やはり素人には「なんとなく気分がいい」「キレイになった気がする」という感覚が大事なのかもしれませんね。
スポーツにおける達人のスランプは習慣に従わないことから起こる?


あるアメリカンフットボールの名コーチ、ダンジーの話が紹介されていました。
ダンジーはアメフトの弱小チームを強チームへと変えていった。
ダンジーは習慣に目をつけて、「選手たちが誰よりも早く動く≒勝つ」ためには考えなくも自然に身体が動くことが大事だとしました。
「敵の〇〇ポジションがこう動いたときは××する」「こういう状況のときは□□に動く」という、きっかけ・ルーチンの訓練を何度も選手たちに施した。この場合の報酬は勝利ですかね?
すると、最初は勝てなかった相手にも徐々に勝てるようになってきた。
しかし大会の決勝戦になると、選手たちが緊張して(?)考えすぎて「きっかけ→ルーチン」のプレーができなくなる。
つまり習慣に従ったプレーができなくなり、負ける。
スポーツにおける達人のスランプとは、考えすぎていつものプレーができなくなることと以前読んだ書籍で紹介されていましたが同じことですね。
スポーツじゃなくても、一般人が無意識にやってる階段を下りる動作も、ふとした瞬間に左脚から降ろすか?右脚から降ろすか?迷子になって(考えすぎて)ぎこちない動作になることあるよね
おそらく、そこそこの年齢の人なら階段は生まれてから何千回~何万回と上り下りしてるのでスポーツでいう所の達人レベル。
いままで習慣で階段を上り下り→考えてしまって、動作がおかしくなる→場合によってはケガをすることも。
スランプ状態≒考えだすと、中々抜けれないですよね
いつもの「きっかけ」が重要なのかな?
この記事の執筆者は暗示にかかりにくい体質なので、「いつもと同じ」と心の中で唱えても中々ハマりにくくて困るところ・・(^^;
スランプに陥ったとき「きっかけ→ルーチン」に、しばらく戻れなくなります。
ニコチンやアルコール依存症から抜け出すために大事なことの1つは、自分を信じること?


繰り返しですが・・「きっかけ」と「報酬」は今までのものを使い「ルーチン」を変えることが依存症を抜け出す方法だと解説されています。
アルコール依存症を例に出すと・・
きっかけ:ストレスを感じる
ルーチン:酒を飲む
報酬:ストレス解消
※本来はストレスの原因まで特定しなければならないんですが、ここでは割愛します(詳しくは後述)
↓
つまりストレスを解消をするために別のルーチン(酒を飲む以外)を行いましょうという、ありふれた話。
たとえば、ストレスでタバコを吸ってるような人だと「犬吸い・猫吸い」でストレスを解消しよう!・・みたいな(動物好き限定ですが)
データによれば、習慣の入れ替えのテクニックを実践したアルコール依存症患者は ほぼ禁酒できたが、それは人生で大きなストレスにさらされるまでのことだった。
習慣の力より
ストレスを受けた時点で、どれだけ新しいルーチンを受け入れていようとも かなりの人数がまた酒を飲み始めたのだ。
しかし、何らかの偉大なる力が自分の人生に加わったと信じている患者は、そうでない患者よりもストレスの多い時期も酒を飲まずに乗り越えられていたそうです。
大切なのは神ではなく「信じること」そのものが差を生む。
いったん、何かを信じることを覚えると、その能力が人生の他の部分にまで影響を及ぼし「自分は変われる!」と信じ始める。信じることこそが、作り変えた習慣のループを永遠の行動に変える要素。
なんかちょっと胡散臭くなってきたけど、「自分は変われる!」と信じることが大事と色んな書籍や人が言ってるよね
「きっかけ」と「報酬」は変えずに「ルーチン」を変えること+自分は変われると信じること→最悪のストレスにさらされた瞬間にも新しいルーチンを貫くことができる。
これは、この記事の執筆者には中々ムズかしい問題(^^;
いままで盲目的に信じていたことが全部間違いだった・・という経験があるので。
真実の可能性、成功率や失敗率をパーセンテージで予測することはできますが、パーセンテージが低いことや、まったく予測がつかないことを脳死で信じることはできませんね。
これは(書籍でいわれている)同じ目標の仲間がいてもいなくても変わらないし、なんならソロプレイしてた方がいいまである。
何をやるにも劣ってる自分からみたら、仲間の存在が挫折の原因になり得る。
自分は典型的な相対比較でダメになるタイプですし。
ただ、自分と似た能力や状況の人が頑張ってる姿は力になるなぁとは思います
成績のよい学生は自制心が高い?~自制心はIQ(知能指数)を凌駕する


意志力≒自制心を発揮できる学生は概して、成績が良く難関校への入学許可を勝ち取ることが多いと書籍でいわれています。
自制心の高い学生は、
・欠席も少なく、家でテレビを見る時間が短く、宿題により多くの時間をかける
・あらゆる学業成績の面で、衝動的な学生を上回った
・・と言われています。
学生の成績を予測するとき、IQ(知能指数)よりも自制心を測った方が正確な予測ができるとさえ言われている。
また年間を通して、学生の成績が上がるかどうかも自制心で予測することができるが、IQでは それができない。自制心は才能よりも大きな影響を与える。
自制心は環境の影響(ストレス環境など)を受けるのは有名ですが、生まれつきの「遺伝」の影響も受けやすいと前に読んだ書籍でいわれていますね
ちなみに、この記事の執筆者は自制心もグダグダです(^^;
なので締切を設定しないと、いつまでも怠けてしまうし、締切があっても長期戦だと体力を消耗しすぎて怠けてしまうときがある。
自制心≒ストレス耐性が高い人がうらやましいですね。
強いストレスや困難に襲われた時どうするか?事前に考えておくことで成功率がアップ
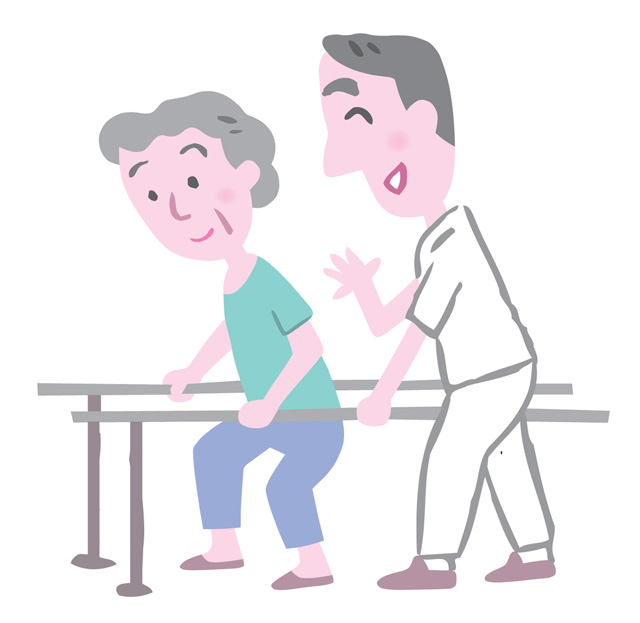
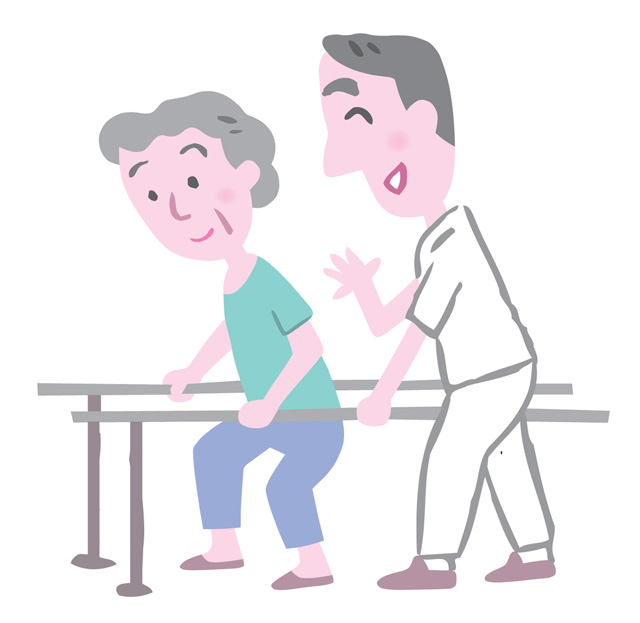
手術後にリハビリの一環として、近所を散歩する・・という計画を立ててる患者たちが紹介されていました。
リハビリは多少の痛みを伴います。
Aさん:近所を散歩しているときに「痛みが出たらどうするか?」まで織り込んでいた
Bさん:近所を散歩するという計画のみ立てた
↓
結果として、Aさんの方が最後までリハビリを続けられたそうです。
Aさんはリハビリとして、歩いて妻を駅まで迎えにいくという目標を立てた。駅に行けば妻に会える(報酬)・・というように設定。
やっぱり「楽観思考」だけじゃなく「悲観思考」の両方を持つことが大事だね
・楽観思考は上手くいくと信じること
・悲観思考は挫折の危機があるという可能性を考えること
Bさんは期待が高すぎた可能性もありますね
期待しすぎると、失敗したときのダメージが大きくて挫折しやすいですし
書いてて気づきましたが、信じること≒期待すること。
信仰が強すぎると失敗を受け入れられなくて認知が歪んだり、失敗を受け入れたときのダメージが大きいので諸刃の剣なんですよね。
この記事の執筆者は、やっぱり盲目的に信じることはできないかなぁ(^^;
ほかに書かれていたのは・・
社員教育が徹底されているコーヒーショップのスターバックスは、社員が厳しい状況(客とのトラブルなど)に直面した時に使える新しいマニュアルを作成したそうです。
そのマニュアルには例えば、顧客が怒鳴りはじめたとか、支払いの列が長くなりすぎたといった特定のきっかけに、どう対処すればいいかが書かれている。
店長は そのような状況が起きたと仮定して、店員に何度もロールプレイングをさせる。
やがて、その対応が自然と無意識にできるようになるまで教育するそうです。
この記事の執筆者は子供のころから怒られる機会が多かったですが、(子供のころは)慣れることはなかったし、緊迫した状況だと力を発揮できないパターンが多かった。
ポンコツ人間でも訓練したら、上手く対処できるんでしょうかね?
ある程度の大人になったら「ああ、またか・・」と怒られることに慣れて、緊迫した状況になると成果は諦めて(期待しなくなるで)対処していましたが。
自分でコントロールできない状況or自分でコントロールできる状況


仕事やプライベートでも自分でコントロールしてる感覚がないと高ストレスにさらされるのは有名な話ですよね。
書籍でも、ストレスを減らす方法の1つとして紹介されていました。
自制心を必要とする作業を頼まれたとき、それが自分自身の望みでもあるとき、自分で選んだと感じられる。あるいは誰かの役に立つ作業なので、満足感が得られるなどは苦しいと感じる度合いが減ります。
習慣の力より
しかし、ただ命令に従っているなど、自分の意思が全く反映されていない場合は意志力の筋肉が消耗するスピードが はるかに早い。
ここに目を付けたのが企業や組織。
社員に責任者意識、つまり物事を自分で動かしている意思決定の権限を持っているという感覚を持たせるだけで、仕事に つぎ込めるエネルギーと集中力が大きく増加する。
組み立てラインで働く社員に生産計画と労働環境に関する小さな決定を行う権限を与え、その社員を詳しく調査したそうです。
①特別な制服をデザインし、シフトを決める権限を与える他は何も変えない
②製造プロセスも同じだし、給料も前と同じ
③しかし、2ヶ月のうちに その工場の生産力は20%も向上した
④社員の休憩時間が短くなり、ミスも減った
⑤物事を自分で動かしているという感覚を与えることで、社員はより大きな自制心を発揮できるようになった
雇用されてる側としては「休憩時間を減らして、生産性を上げたのに給料が変わらないだと!?」と怒り狂いそうですが、データとしては こういう結果が出てるみたいだね
この記事の執筆者もルールでガチガチに縛られてる大企業より、ある程度ユルい中小企業の方が働きやすかったですし、比較的ながく続いていました。
高ストレス+福利厚生を取るか?低ストレス+働きやすさを取るか?って感じですね。
ヒットしなかった良い曲をヒット曲に変える方法~サンドイッチ方式


書籍では、音楽家や統計の専門家たちが大ヒット間違いなしだと期待していた「Hey Ya!」という当時の新曲が紹介されていました(おそらく過去、アメリカでヒットした曲だと思います)。
しかし、実際にラジオでHey Ya!を流してみると、曲が流れだした瞬間、リスナーたちは一斉にラジオチャンネルを変えたといいます。
なぜかというと、その曲には馴染みがなかったから。
そこでラジオ局がHey Ya!をヒットさせるために取った方法がサンドイッチ方式。
既にヒットしている曲と曲の間にHey Ya!を挟んで流した。リスナーに馴染んでもらうために。
のちにHey Ya!は大ヒット曲となる。
さらに、リスナーのいうことを真に受けてはならない例も紹介されています。
アメリカではラジオ局がアンケートとしてリスナーに電話をかけ、ある曲の一節を聞いてもらう機会があるそうです。
この曲は100万回も聞いた。もう飽きてるよとリスナーが言っても無意識の部分が この曲知ってる、もう100万回も聞いている、一緒に歌えると叫んでいる。
習慣の力より
つまり、スティッキーな曲というのは、リスナーがラジオに期待している曲なんです。
脳は実はその曲を聞きたいと思っている、誰にとっても馴染みがあり、既に聴いていて好きになっている。ここで流れるべき曲だと感じるのです。
※ここで書かれているスティッキーは馴染みがあるという意味(本来の意味はベトベトする・粘々するなど)
学校祭のステージとか一般ライブでも、誰も知らないオリジナルソングより誰もが知ってる曲の方が観客に喜ばれますよね
あとは、習慣は無意識下で行われてるから、リスナーが自分自身の欲求を認識できてないってパターンもあるってことだね
ドラマやアニメの主題歌やED曲は何度も聴くことになるからヒットしやすいってことですね。アニメやドラマで使われなかった曲と比べて。
私たちはある行動を習慣にすることで、決断を次から次へと迫られることなく暮らしていける。
それと同様に「音」を聞くときも習慣に従ってしまうのは、それがなければ自分の子供のサッカーの試合で子供の声やコーチの笛を道路の騒音と聞き分けることさえできなくなるからだと書籍で言われています。
重要な音と無視しても差し支えない音を無意識のうちに分けるよう、私たちの耳は習慣づけられている。
たとえ聞くのは初めてでも馴染みのあるサウンドを気に入るのは、まさにそれが理由。
音楽だけじゃなくて、マンガとかもそうだなぁと思いました(^^;
悪役令嬢ものが流行れば市場は それ一色になったり、転生ものが流行れば今度は転生もの一色になったり。
似たような作品やテーマが連発になるのは、ちゃんと意味があるんですね。
悪い習慣を断ち切り、良い習慣を根付かせる方法~きっかけ・報酬の特定


この書籍の著者の悪い習慣の例が示されていました。
※後に、きっかけ・報酬を特定して改善できたそうです
・午後3時半ころになると毎回カフェへいき、友人とおしゃべりしながらチョコチップクッキーを買って食べてしまう
・そのことを何度も著者の奥さんに怒られていた
・この習慣を変えたいと著者は思った
奥さんが怒ったのはチョコチップクッキーの食べ過ぎは健康によくないから・・ってことでいいのかな?
この習慣を変えるには「きっかけ」と「報酬」を特定しなくてはなりません。
つまり、本質的な欲求を特定するということですね。
きっかけ:空腹?ストレス?散歩したい?おしゃべりしたい?午後3時半という時間?
ルーチン:カフェへ行って、友人とおしゃべりしながらチョコチップクッキーを食べる
報酬:チョコチップクッキー(甘い食べ物)?空腹を満たす?軽く運動したかった?友人とのおしゃべりでストレス発散?
※ストレスだった場合、自分が何でストレス発散できるのかも検証する必要がある
ルーチン以外は不明なので、1つずつ検証していかなくてはなりません。
<きっかけの検証>
検証①:チョコチップクッキーをリンゴに変える
検証②:カフェへは行かず散歩をしてみる
検証③:時間を午後2時にしてみる
検証④:チョコチップクッキーは食べず、友人とおしゃべりのみする
↓
それぞれ検証して感じたこと・頭に浮かんだ考え(満足度など)をメモする。自分は何を欲しているのか見極める。
<報酬は何か?>
①の結果:満足度は変わらない
②の結果:気晴らしにはなったが満足感は薄い
③の結果:午後2時に休憩しても、午後3時半前後で集中力が切れる
④の結果:チョコチップクッキーを食べなくても、満足感を得られた
検証の結果、午後3時半前後になると、著者はチョコチップクッキーを食べたいのではなく「友人と おしゃべりしたい」というのが本当の欲求だとわかる。
本当の欲求が分かってから著者はタイマーをかけ午後3時半前後になると、チョコチップクッキーは食べず、毎回友人を探して、10分程度おしゃべりするようになったそうです。その時間に友人が見つからないときもあったそうですが・・。
毎日甘いものを食べてしまうという悪い習慣を別の習慣に変えた・・という著者の体験談。
酒断ち・タバコ断ちなどは失敗を重ねて、成功すると書かれています。
悪い習慣を断ち切るには「検証&失敗」の試行錯誤が欠かせない。
ついでに、この記事の執筆者の場合もシミュレートしてみましょう(今のところ未検証ですが、メモとして残しておきたい)。
悪い習慣→「イラスト作業や執筆作業のときに、ついついSNSやYoutubeを頻繁にみてしまう・お菓子をつまんでしまう」
きっかけ:集中力切れ?山場がシンドい?先が長すぎる?仕事で疲れている?糖分や塩分が足りない?
ルーチン:SNSやYoutubeを頻繁にみてしまう、お菓子をつまんでしまう
報酬:脳の疲れを癒す?脳にブドウ糖補給?現実逃避?
<きっかけ検証>
検証①:30分作業したら5分だけSNSかYoutubeをみる
検証②:塩あめを口に入れる
検証③:作業を分解する(1日でやる作業分量を決める)
検証④:休日の作業は午前と夜のみで昼間は遊ぶ(昼が1番集中力が切れるため)
↓
まだ試してないので予測ですが・・
・SNSやYoutubeをみても心が休まった気がしないので①は違う気がする
・空腹でも集中できるときはできるので、塩分や糖分が足りないも違う気がする
・作業の先が長いが1番怪しい、簡単に作れるショート動画作業のときは結構集中してるので
・仕事の疲れが次の日に残ってることは少ないが、真夏や真冬だと夜の眠りが浅くて疲れが残ってるときがある
③が一番怪しいという予測ですが、執筆もイラストも拘れば拘るほど時間を投入できるので、作業量の予測が難し点は困るところ・・。やっつけ仕事でいいなら計画も立てやすいですが。
あとは現在、新しい挑戦として簡易的なマンガを描く作業もしていますが、これも初挑戦に近いので時間配分がわからない件。
この記事の執筆者は、作業を分解するためのノウハウ(書籍?)が必要そうです(^^;
余談:過去に「罪となった習慣」と「罪に問われなかった習慣」があった?


アメリカで過去、習慣のせいで殺人をしてしまった男性とギャンブル中毒になった女性が紹介されていました。
殺人をしてしまった男性の場合
・生まれつきレム睡眠行動障害(寝てるときに無意識に身体が動く、たいていは暴れる)があった
・しかし、誰かに危害を加えたことは今までなかった
・男性は妻と車中泊の旅行中、妻と並んで寝ていた
・夢の中で妻が男に襲われていたので、男の首を絞めた
・男性は男の首ではなく、現実で妻の首を絞めて殺してしまった
・しかし、裁判では無罪となった(保釈された)
※このレム睡眠行動障害は書籍では夜驚症と言われていて「習慣」として扱われています
ギャンブル中毒にさせられて(?)カジノを訴えた女性の場合
・女性は家庭でストレスを抱えていた
・家事や育児をがんばっても誰からも感謝されないというストレス
・そんなときカジノへ行ってストレス解消をしていた
・カジノ側も女性を接待したり、旅行券をプレゼントして女性を何度もカジノに呼び込む
・女性は段々とカジノへ行く頻度、使い込む金額が大きくなり破産
・その後、女性は改心してギャンブル断ちをしていたが、女性の両親が他界して強いストレスにさらされた
・女性は またカジノへ行って、両親が残してくれた遺産をすべて使いつぶした
・女性はカジノへのツケが払えなくなり、カジノは女性を訴える
・女性もカジノを訴える
・女性が敗訴する
ギャンブル中毒の女性が責任を問われる一方で、殺人をした男性は釈放されてしかるべきというのは、男性は自分の殺人に繋がる行動パターンの存在すら知らず、ましてや、それをコントロールすることもできないと判断されたからだそうです。
しかし、ギャンブル中毒の女性は自分の習慣に気づいていた。
知っていたからには、それを変える責任がある。彼女がもう少し努力をしていたら、ギャンブルの習慣を抑えることができたかもしれない。
もっと大きな誘惑を前にしても屈しなかった人は、たくさんいる・・という内容でした。
殺人をしてしまった男性は妻と仲が良かったということなので気の毒だけど、カジノを訴えた女性は凄いな・・さすが訴訟の国アメリカ
しかし書籍を読んだ感じだと、カジノから女性への誘惑も中々ひどかったですけどね
日本でもホストが女性に支払い能力を超えたツケ払いをさせる例が多いので、他国事でもない気がしますが・・
その他、面白かった余談など~ギャンブル中毒者の脳と記憶違いが多い人の特徴


・ギャンブル中毒者の脳
「病的なギャンブル中毒者」と「ほどほどのギャンブラー」数人の脳内を調べた実験が紹介されていました。
・両者にパチンコ(正確にはスロットだが)の映像を見せて、脳内を調べる
・勝ちそうなとき病的なギャンブル中毒者の方が、脳の報酬系や感情に関わる部位が活発になる
・病的なギャンブル中毒者がニアミス(当たりそうで外れる演出)のときも、上記の脳部位が活発になる→つまり当たり(勝ち)と認識している
・ほどほどのギャンブラーの人たちはニアミスは外れ(負け)と認識する
・ほどほどのギャンブラーの人たちがニアミスを見たとき、むしろ不安を感じ、違う習慣の引き金が引かれる→もっと悪くなる前に やめた方がいいのか?と
パチンコで やたら「当たりそうで当たる」とか「外れそうで当たる」とか「当たりそうで外れる」演出があるのは、この為なんですね・・(^^;
病的なギャンブル中毒者はギャンブルで脳汁がドバドバ出るうえ、認知も歪んでいるってことか・・
この記事の執筆者は こういう認知の歪みが怖くて、可能性が低いことを信じれないんですよねぇ
・記憶違いが多い人の特徴
事件が起きて警察が目撃情報を集めるとき、「記憶違いをする目撃者」と「そうじゃない目撃者」の違いの話が紹介されていました。
内容としては、警察が目撃者に尋問するとき(警察が)友好的な態度を取れば取るほど、目撃者は記憶違いをするそうです。
目撃者は相手を喜ばせたいという「習慣」の引き金が引かれて、事実と異なることを思い出すと書籍で言われています。
これは予想外ですね。
厳しく尋問された方が(追い詰められて?)記憶違いを起こしそうなもんですが・・。
前に読んだ書籍では、追い詰められると視野が狭くなって、狭い範囲のものしか覚えていないという現象になると書かれていました。
強盗に被害者がナイフを突きつけられる→その後、強盗が逃走→警察が被害者に犯人の特徴を聞き出すが、被害者はナイフのことしか覚えてないという話。
リラックスして話すのと、相手を喜ばせたいという気持ちはイコールじゃないかな・・?(^^;
まとめ:個人的にはサボり癖に使ってみようと思いました


・自制心>頭のよさ
・習慣の力を知っていれば、〇〇中毒を断ち切ることができるかも?
・習慣という習性を知っていれば、商売にも生かせる可能性がある
・強いストレスにさらされた時や困難にブチ当たった時にどうするか?予め考えておく必要がある
・本質的な欲求を特定するには検証&失敗の試行錯誤が必要
・きっかけ→ルーチン→報酬の話で、ルーチンだけ変えるという考えが役立った
自制心≒ストレス耐性。
前述していますが・・ストレス耐性って(環境の影響もあるが)ほぼ遺伝子で決まるらしいので鍛えるのは難しそうです(^^;
この記事の執筆者はストレス耐性が普通~少し弱いくらいなので、足りないぶんは 書籍等で勉強して知識をつける→挫折しながら試行錯誤していきます。
挫折する可能性も織り込んでおけば、必要以上に挑戦にビビることもなくなるし。
習慣の力は、自分を変えたい人やマーケティングの参考にしたい人にオススメな書籍です(一見ページ数が多い書籍に感じますが、1/3くらいは参考にした文献や用語の解説です)↓
本・書籍ランキング
にほんブログ村